

税金支払いをなるべく減らして、お得に経営・生活したい。
いますぐできる節税のコツやテクニックを教えて!

この記事の信頼性
この記事の著者「こばん」は、簿記とFP技能士の資格を持つ "会計とお金の専門家" です。 複数メディアで節約や節税、資産運用に関する情報発信をしています。 詳しいプロフィールはこちらで確認できます。
8つの節税対策
- 青色申告をする
- なるべく多く経費計上する
- 小規模企業共済に入る
- 経営セーフティ共済に入る
- 保険に入る
- iDeCoに入る
- 医療費控除を受ける
- ふるさと納税をする
個人事業主・フリーランスが絶対にやるべき節税対策8選

節税対策①:青色申告をする
個人事業主やフリーランスにとっての節税対策の第一歩は、青色申告をすることです。 確定申告には、青色申告と白色申告があります。 青色申告とは、複式簿記による記帳を行い、損益計算書と貸借対照表といった決算書を作成する確定申告の方法です。 白色申告より作成する書類が多くはなりますが、節税メリットは絶大です。 たとえば青色申告で確定申告を行なうと、最高で65万円の特別控除を受けることができます。 一方の白色申告だと、10万円の控除がされるのみです。 年1回の確定申告に手間を掛けるだけで、数十万円規模の節税ができるのです。 節税したいなら、必ず青色申告をしましょう。参考
「帳簿作成作業を、もっと簡単にしたい!」とか「会計の専門知識がないから不安」という方も多いでしょう。 そんな方は、会計ソフトを利用しましょう。 導入費用は年1万円程度です。これで数十万円の節税ができるなら、十分に元が取れます。 会計ソフトの選び方は、以下の記事で解説しています。
-

個人事業主のための会計ソフト3選|選び方のポイント3つを解説
続きを見る
節税対策②:なるべく多く経費計上する
つぎは、なるべく多く経費計上することです。 個人事業主やフリーランスの税金は、課税所得の大小によって決まります。 課税所得とは、「課税所得=売上-経費-控除」の式で計算されます。 つまりなるべく経費を多く計上すると、その分、課税所得が少なくなるのです。 節税を徹底するには、「事業に関係する費用は、すべて経費にする」という考えを持ちましょう。 以下6つを理解しておくと、抜け漏れなく経費計上できます。経費計上のコツ①:家事按分
1つ目は、家事按分です。 個人事業主の方には、自宅兼事務所というケースも多いと思います。 その場合には、家賃や水道光熱費を実際に仕事で使っている面積や時間で按分して、事業の経費とすることができます。
こばん
この面積や時間にもとづき事業経費を按分算出する方法を、「家事按分」と呼びます。
参考
「どんなものが経費にできるの?」という疑問は、以下の記事で解消できます。
-

個人事業主の節税対策|30の事例でわかる経費計上できる費用科目
続きを見る
経費計上のコツ②:税金
2つ目は、一部の税金も経費計上することです。 意外と見落とされがちですが、税金にも一部、経費計上できるものがあります。 これを漏れなく経費計上することで節税できます。経費計上できる税金
- 事業税
- 消費税
- 固定資産税
- 自動車税
- 自動車所得税
- 不動産所得税
- 登録免許税
- 印紙税
経費計上できない税金
- 所得税
- 住民税
- 相続税
- 贈与税
- 交通反則金などの罰金
- 加算税
- 延滞税
経費計上のコツ③:開業費
3つ目は、開業費です。 個人事業主やフリーランスとして独立する前に使ったお金も、経費に計上できます。 開業前に使った費用は後日、「開業費」として確定申告に反映できるからです。 開業費の適用範囲は広く、「開業の準備にかかったもの」を証明できれば基本的にすべて認められます。開業費の例
- 開業のためのセミナー参加費用
- 調査のための旅費、ガソリン代
- 通信費用
- 打ち合わせ費用
- 関係先への手土産
- 開業までの借入金利子
- 広告宣伝費
- パソコン購入費用
-

開業前に忘れずにやるべき4つのこと|節税対策と生活に困らないコツ
続きを見る
経費計上のコツ④:短期前払費用の特例
4つ目は、短期前払費用の特例を利用することです。 継続的なサービスの提供を受ける契約で、数カ月分あるいは1年分の代金をまとめて支払う場合があります。
こばん
たとえば、インターネットのサーバー代や雑誌購読料などが当てはまります。
経費計上のコツ⑤:少額減価償却資産の特例
5つ目は、少額減価償却資産の特例を利用することです。 基本的に、単価が10万円以上するものは長期間利用できる「固定資産」とみなされます。 固定資産は減価償却という方法で数年に分割して必要経費に計上することになります。 つまり、支払いは1度に済ませた場合でも、その金額をその年中に必要経費とすることはできないのが原則です。 しかし青色申告で確定申告をすれば、30万円未満の固定資産について一度に必要経費とする優遇措置を受けることができます。 これを「少額減価償却資産の特例」と言います。 少額減価償却資産の特例を利用すれば、20万円のパソコン購入費用も一度に経費にできます。 出費があった年に節税できるので、資金繰りが楽(らく)になります。注意ポイント
少額減価償却資産の特例は、利用できる期限が決まった時限措置です。 この記事を書いている2022年1月時点では「令和4年(2022年)3月31日」が期限とされていますが、延長の可能性もあります。 詳しくは、 国税庁『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』 で最新の情報をご確認ください。
経費計上のコツ⑥:所有から利用に切替
6つ目は、「所有」から「利用」への切替することです。 所有している場合には固定資産として見なされ経費計上できなものも、レンタルやリースにすると利用料を経費計上できます。 同じものでも、所有から利用に変更するだけで、節税になるのです。 たとえばクルマです。 購入・保有からカーリースやサブスクリプションサービスの利用に切り替えると、毎月の利用料が全額経費計上できます。 それも車両代だけでなく、任意保険やメンテナンス費もコミコミですべて経費にできるので、とってもお得です。 以下の記事で詳しく解説しています。-

個人事業主のクルマ節税|トヨタKINTOを選ぶべき7つの理由
続きを見る
節税対策③:小規模企業共済に入る
続いて、小規模企業共済に入ることです。 小規模企業共済とは、国が運営する、個人事業主などのための退職金制度です。 小規模企業共済に加入して支払った掛金月額は1,000円~70,000円の範囲で、その全額を控除することができます。 最高で月70,000円ということは、70,000円×12カ月=84万円もの控除を受けることができます。 また前払いをした場合には、向こう1年以内のものであれば控除することができるので、最高で168万円の所得控除を受けることができます。 個人事業主などの小規模企業経営者だけが利用できるお得な制度です。 短期的には節税に、長期的には老後の生活資金形成につながりますので、ぜひ活用しましょう。
こばん
脱サラして独立する人は、しっかり考えておくべきポイントです。 会社員時代に加入していた厚生年金がなくなる分、個人事業主やフリーランスは自分で老後資金を蓄えておく必要があります。 このような国の制度を利用して、自分の生活を守りましょう。
節税対策④:経営セーフティ共済に入る
経営セーフティ共済に入ることも、節税になります。 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先事業者が倒産した際に中小企業や個人事業主が連鎖倒産したり経営難に陥ったりすることを防ぐための共済制度です。 取引先事業者が倒産した際には、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借り入れることができます。 掛金は損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるという税制優遇があります。 掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選ぶことができて、途中で増額・減額できます。 もしもの場合に備えると当時に、賢く節税できるのでおすすめです。 参照:中小機構「経営セーフティ共済」節税対策⑤:保険に入る
つぎは、保険に入ることです。 生命保険や介護医療保険、個人年金などに加入すると、最大で12万円(※)を所得から控除することができます。 (※)...契約の締結日が平成23年12月31日までの旧契約の控除額は上限10万円、新契約の控除額は上限12万円です。 旧契約と新契約の両方を契約している場合には、①旧制度のみ、②新制度のみ、③旧制度と新制度の併用、のいずれかを選択することができます。 参照:国税庁『生命保険料控除』 また地震保険料も、控除対象になります。 最大で5万円を所得から控除できますので、自宅を所有している方は加入しましょう。 参照:国税庁『地震保険料控除』
こばん
とはいえ、保険の入りすぎには要注意です。 保険料は、一部節税効果があるとはいえ、支払い総額は多額になります。 日本には世界一手厚いと言われる公的保険制度があります。 民間保険はなるべく絞り込んで、必要最小限にするのがおすすめです。
節税対策⑥:iDeCoに入る
つぎに、iDoCoを利用することです。 iDeCo(個人型確定拠出年金/イデコ)とは、自分のための年金を自分で積み立てる制度です。 掛金を払いながら預金や投資信託などで運用し、その運用益が非課税になるばかりでなく掛金が全額まるごと所得控除の対象となります。 積立時の掛金については、毎年所得税と住民税が軽減されますし、利益が出てもその利益に税金はかかりません。 また、受取時にも一定額まで無税となる大変メリットのある制度です。 参照:国民年金基金連合会『iDeCo公式』節税対策⑦:医療費控除を受ける
続いて、医療費控除です。 医療費控除とは、年間の医療費が10万円を超えた分を所得から控除できる制度です。 たとえば年間の医療費が15万円なら、5万円を所得から控除できるのです。 医療費とは「治療を目的とした医療行為に支払った費用」のことで、たとえば以下のようなものです。医療費になるもの
- 医師や歯科医師による診察・治療
- 治療目的のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術
- 助産師による分娩の介助
- 治療や療養に必要な医薬品の購入
節税対策⑧:ふるさと納税をする
さいごは、ふるさと納税です。 ふるさと納税をすれば、確定申告で寄附金控除を活用できます。 これにより、所得税と住民税を軽減することができるのです。 寄付金控除の金額は、実際に寄付した金額から2千円を引いた金額です。 また、都道府県や市区町村に対して寄附すると、寄附先から特産品をもらうことができます。 そのためふるさと納税は、実質2千円の自己負担で各地の特産品をもらえる、うれしい仕組みになっています。 日ごろは買えないぜいたく品をもらって楽しむのも良いでしょう。 またティッシュやお水、ビールなどの日用品を返礼品としてもらえば、生活費を節約することもできます。 注意点は、年収や家族構成、お住まいの地域により、控除の上限額が決まっていることです。 控除上限額は、さとふるさいごに(知識は武器です!)
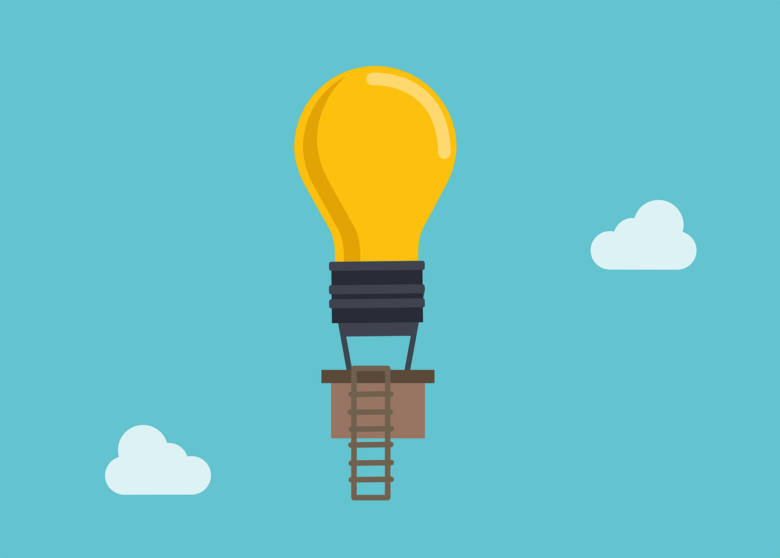 この記事では、以下8つの節税テクニックを紹介しました。
この記事では、以下8つの節税テクニックを紹介しました。8つの節税対策
- 青色申告をする
- なるべく多く経費計上する
- 小規模企業共済に入る
- 経営セーフティ共済に入る
- 保険に入る
- iDeCoに入る
- 医療費控除を受ける
- ふるさと納税をする

そうはいっても、何からどうやって情報収集すれば良いかわからない...(泣)
\ この記事が気に入ったらフォロー /
あわせて読みたい
-

年間20万円のお金を生む節約術|固定費を削減するコツ10選
続きを見る





